- 走行コース:徳島−貞光−明渡橋−小島峠−落合峠−深渕−桟敷峠−半田−徳島
- 走行距離:約200km
- 所要時間:12時間
 |
| 明渡橋 |
 |
| 小島峠 |
 |
| 落合峠南側の展望 |
 |
| 落合峠東側の展望 |
徳島市内からみれば落合峠は剣山よりも山奥にある峠。 三加茂から桟敷峠を経由するルートが最短だが、以前は未舗装区間が残っていたから、ロードで行こうと思えば東祖谷側の国道439号からアプローチするしかなかった。 徳島市内からの日帰りツーリングの限界は剣山というのが常識だっただけに、落合峠の日帰りは困難な課題として残っていた。 クルマで貞光や三加茂まで行ってスタートすれば比較的容易で、実際に何人かの人たちはそのようなツーリングを(大抵はMTBで)行っていた。 それだけに、なんとか徳島市内からロードによる日帰りを実現させたかった。
結局、落合峠へのアプローチとして選んだのは県道261号菅生伊良原線。 小島峠を越えていくルートだった。2004年7月の中旬、朝6時過ぎに徳島市内を出た。 貞光に着く頃には陽も高くなり、暑くなってきたが、国道438号で貞光川沿いに走ると木陰が多く、涼しくなった。 一宇橋の上流約800mで明渡橋を渡り、県道菅生伊良原線へ。 ここより小島峠まで距離約11kmの登り。 剣山へのルートとして利用される国道438号と違って、こちらはほとんど通行がない。 明渡橋から5kmほど入り、道が谷筋を離れると勾配がきつくなった。 激坂である。 舗装は荒れ、落石や砂利が多い。 なんと道端の草むらでイノシシが地面に頭を突っ込んでいた。 タワシのような毛に覆われた背中を震わせて一心不乱に何かをほじくっている様子。 真横を通る私達にもまったく気づいていなかった。 それくらい普段から人っ気のない道ということなのだろう。
小島峠を祖谷側へ下り切ると、菅生で国道438号と合流する。 ここから下り基調で西へ約8km走り、落合峠の登りに取り付ついた。 木立の中を登り、トラバース気味に進んでいくと視界が開けた。 急斜面に落合の集落(※1)が姿を現す。 祖谷には江戸の中期から明治期にかけて造られた民家が何軒も残っており、特に落合地区に多い。 峠までの登りは14km、平均勾配6.9%、峠の標高は1520m。 こちらも所々にアスファルトの剥離や落石が見られ、部分的ではあるが、ひどく荒れたコンクリート舗装もあった。 峠には木がなく、笹原が広がっている。 剣山系では高い山の頂は笹原となっていることが多いが、峠で笹原の見られる場所は少ない。 他にはイザリ峠などがあるが、自転車で行ける峠では落合峠しかない。 落合峠は展望も素晴らしい。 天候に恵まれれば、南に三嶺から天狗塚にかけての山並みを遠望し、東には矢筈山からサガリハゲ山、西には寒峰の頂を見渡すことができる。 県内最高の峠だ。 単に自転車で行ける県内で最も標高の高い峠という意味だけでなく、峠の雰囲気、展望、アプローチなど、峠としての要素を総合的に評価して県内最高といえる。
峠からは深渕へ下り、桟敷峠を経て半田に下りることにした。 当初は再び落合へ下り、剣山経由で戻るつもりであったが、もはや時間的に無理だった。 峠から深渕までは2〜3kmの未舗装区間があったが、この際やむを得なかった。 下りなのでロードでもなんとか走れたが、途中には土ではなく、岩盤がむき出しになっている所もあった。 未舗装区間はその後、2006年に全線舗装された。 途中の深渕はミステリアスな雰囲気漂う集落で、何度通っても人の気配がないが、 三好市のHPによれば2009年1月末現在6世帯9名の住民が登録されている。 小学校(※2)の建物も残っていて、かつてはこのような辺鄙なところに学校があったことに驚かされる。
深渕の標高は900m近い。
桟敷峠の標高が1000mを少し越える程度なので、深渕から桟敷峠までは100m登っただけであっけなくたどり着いた。
桟敷峠からは水の丸を経由して半田へ下った。
半田からは再び国道192号で徳島市内へと戻った。
距離は約200km。
所要時間は休憩も含めて12時間だった。
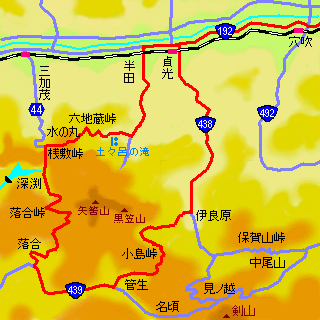
※1 落合地区は2005年に国の重要伝統的建造群保存地区に指定された。
※2 落合小学校深渕分教場が作られたのは明治34年。