川井峠に向かうときは国道438号線を西に向う。
徳島市内から438で佐那河内から神山へ入ってもいいが、
夏場なら県道21号・20号で鮎喰側沿いに走って神山に入るコースが日陰が多くてお勧め。
鮎喰川の流れは澄んでいて、夏になると県道沿いの川原では家族連れや子どもたちで賑っている。
地理的条件の良く似た勝浦川では近年水質低下により、以前の姿は見る影もないが、
鮎喰川は今でも下流域に至るまで泳げるだけの水質を保っている。
下流から上流に向って走ると、風景の移り変わりが、まるで時の流れを遡っているような気分にさせる。
市街地から農村、山里へと変化していくにつれて、懐かしい風景が蘇ってくる。
それは古めかしい看板であったり、僕たちに手を振る子どもたちの純朴そうな笑顔であったりする。
 |
| 川井峠のしだれ桜、見頃は例年4月10日前後 |
神山町川又まで来ると道の両側に民家が並ぶ。
ここは国道438号線に国道193号線が交わる地点。
沿道には古びた宿が何軒か残っており、古くからここが宿場であったことを物語っている。
分岐点には食料品店があり、寄井にコンビニができるまでは休憩と補給を兼ねてよく立ち寄ったものだ。
ここからは、西に川井峠。南に土須峠、北に倉羅峠が控えている。
県内の主要なヒルクライムの基点といっていい場所だ。
川又を過ぎると、徐々に登り勾配が増してくる。
人家も減り、静かな山里の風情が漂う。
川幅は狭く渓谷と言ったほうがよい。
道幅も狭く、とてもこれが国道とは思えないが、県内の3桁国道では、このような狭隘な区間は決して珍しいものではない。
しかし、自転車で走る分には改良された広い道よりも、狭くても風景に溶け込むような道の方が断然いい。
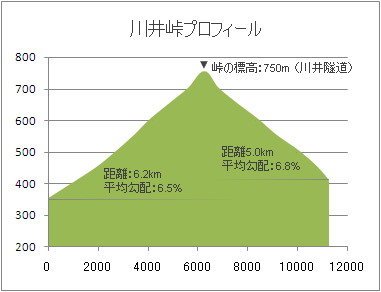
さらに上流に向い殿宮、府殿と過ぎていく。
この辺りは東宮山という山の麓。鎌倉時代に承久の乱によって阿波に流された土御門上皇を祀っているという。
上記の地名は上皇との関係があるようだ。
府殿を過ぎ、鮎喰川の左岸から右岸に渡る橋のあたりから、本格的な登りが始まる。
とは言っても、土須峠や倉羅峠と比べると距離も勾配もワンランクやさしい。
つづら折りを登っていくと最後はトンネルになっている。
標高は約750メートル、盛夏でもここに入ると身が締まるくらい冷やっとしている。
トンネルを抜けると、白い神社があり春には見事なしだれ桜を見ることができる。
また、道の左側にテラスのように張り出したところがあり、天気がよければ、剣山が遠望できる。
峠からは来た道を引き返すか、木屋平村役場まで降りて穴吹に抜けるか、あるいは剣山を目指すかということになる。
剣山は別の機会に述べるとして、ここでは国道492号線で穴吹に抜けるコースを紹介する。
438の分岐点から穴吹までの距離は約28km。
途中には恋人峠というロマンチックな地名もある。
道は穴吹川沿いに緩やかに下っていく。穴吹川は鮎喰川よりさらに澄んでいて四国屈指の清流。
国道192号線から5kmほど上流にあるブルーヴィラの前の川原では、夏になると多くの人で賑う。
山から出てきて国道192号線に合流すると、まるで過去から現在に戻ってきたようだ。
あとは東に進路を取り、一路徳島市内を目指す。穴吹から徳島までは残すところ約40kmの道程である。

川井峠とその周辺